ギャラリー
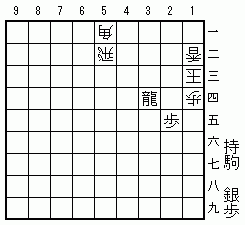
▲4二歩 △同 角 ▲2四銀 △2二玉 ▲2三銀成 △1一玉
▲3二竜まで7手必至
焦点の歩
入門書などで紹介される「歩の手筋」に「焦点の歩」がある。一番ポピュラーなのは「3三歩」だろうか。本局の「4二歩」も振り飛車破りの好手としてしばしば目にする。
必至問題として練ってみたが、同一作があっても何ら不思議ではない。2手目△2三歩などは▲2四銀以下詰み。△4二同角と取るよりないが、7手目▲3二竜で必至が掛かる。(2024/03)
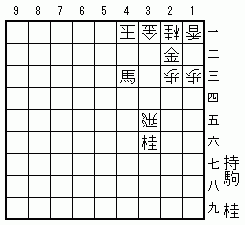
▲3一金 △同 玉 ▲3三桂まで3手必至
桂は跳ねない
どこかで▲4四桂としてみたくなるが、桂は跳ねない。初手▲4四桂は△9二飛▲5三桂△5一玉▲6一桂成△4一玉▲3一金△同玉、3手目▲4四桂は△3九飛打くらいで続かない。
3手目▲3三桂で受けなし。以下△同飛は▲4二金△2二玉▲3三馬①△同桂▲3二飛△2一玉▲3一金まで。①△3三同玉は▲3二飛まで。攻方3六桂がよく利いている。(2023/04)
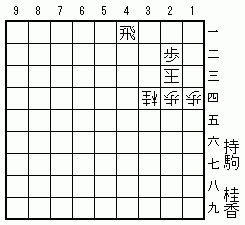
▲3五桂 △2二玉 ▲2三香 △3二玉 ▲4三飛成 △3一玉
▲2二香成 △同 玉 ▲2三桂成 △1一玉 ▲3二竜まで11手必至
一本道と横道
初手▲3五桂、3手目▲2三香と俗手で迫る。玉方は最長最善を尽くし、攻方は手なりで網を絞る。4手目△1三玉は▲1一飛成△1二金合▲2二香成で受けがない。
必至問題の清貧図式は珍しいだろうか。シンプルな初形から、長さの割には分かりやすい一本道とピリッとした横道(4手目△1三玉の変化)が表現できたと思う。(2023/04)
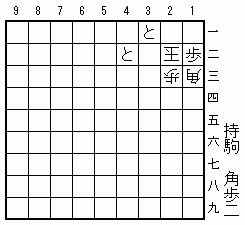
▲3二と寄 △1二玉 ▲2一角 △1一玉 ▲2二と △同 角
▲1三歩まで7手必至
寝取りの手筋(仮)
5手目▲1二歩は打歩詰。そこで▲2二とと捨て、△同角に▲1三歩と垂らせば受けがない。打歩詰に必至あり。
▲2二と~▲1三歩の名調子。相手の駒を動かし、動いた元の場所にチョン。必至問題でときどき見掛ける気がするが、何か呼び方などあるのだろうか。仮に「寝取りの手筋」と名づけてみよう(笑)。必至図から△1三同角は▲1二歩△2二玉▲3二とまで。(2023/04)
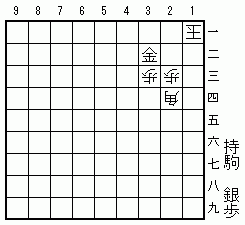
▲2二銀 △1二玉 ▲2一金 △1五角 ▲1四歩まで5手必至
打歩詰に必至あり
3手目▲2一金は▲1三歩以下の詰めろ。受けなしと思いきや、△1五角が打歩詰に誘う佳手。これには▲1四歩と垂らせば今度は受けがない。
「打歩詰に必至あり」。原理をシンプルかつコンパクトに表現できたと思う。詰将棋(「打歩詰に詰みあり」)と比べると、難易度はいかほどか。必至図から△2四角は▲1一銀成、△2四歩は▲1三歩成まで。(2023/04)
